PDCAの大切さ
大阪オフィスからこんにちは!
「PDCA」は生産性や品質の向上を目指し、業務改善・効率化の促進を図る基本的な手法です。しかし、昨今では古い言葉ともいわれ、新しい造語やキャッチーなキーワードが増えてきています。
しかしながら、当社では上場企業の大きな組織のお客様から小さな組織のベンチャー企業や中小企業まで幅広くお取引させていただく中で、どんな組織でも本質的には、そのPDCAのフレームワークの考え方は引き続き大切だと実感しています。

“PDCA“とは
アメリカの統計学者で1950年代の戦後の混乱期に「品質管理の父」と言われ活躍した、アイオワ州生まれのウィリアム・エドワーズ・デミング博士によって提唱されたフレームワークで、Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)の仮説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという考え方です。
Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)とそれぞれのプロセスを順番に行い、最後のステップAction(対策・改善)まで終わったところで、また最初のPlanに戻り、ただ単純に繰り返すのではなく、修正や改善を加えながら次の計画に反映させるところが狙いです。
最近の企業ではPDCAの誤った使い方をする企業は減ったように思いますが、ひと昔の昭和型の企業では、業務改善や新しい取り組みを形式的に、PDCAに嵌めることも散見され、実務を進める上での基本フレームワークとして使いこなしている企業は少なかったように思います。
PDCAの本質的に大切なポイント
通常、組織の中では年間や中期での予算があり、それを実現するための計画があり、その計画を実行に移すためのマイルストーンやタスクがあり、予算に向けた進捗や巡行度合いを管理しながら、見直したり修正したりして目標に近づけていく感じでオペレーションを進めていると思います。
私たちnuloにおいて大切にしているのは、PDCAの”P”や“C”の部分です。
「なぜDX化すべきなのか?」
「どうしてITツール(例えばMAツールなど)を使わないといけないのか?」
など、そもそも当該業務(事業)において、”なぜそれが必要か“という点から現状を分析しながら自分たちなりの仮説を作り、その仮説に応じて、期間を決めてレビューを行い、何が上手くいって何が上手くいかなかったのか、組織の中で把握して、次に活かしていく部分です。
PDCAは描いた計画を実行してから、評価・検証をおこない、対策と改善まで進んで1セットです。実行だけでは、プロセスが完結せず、その目的を達成することが出来ません。
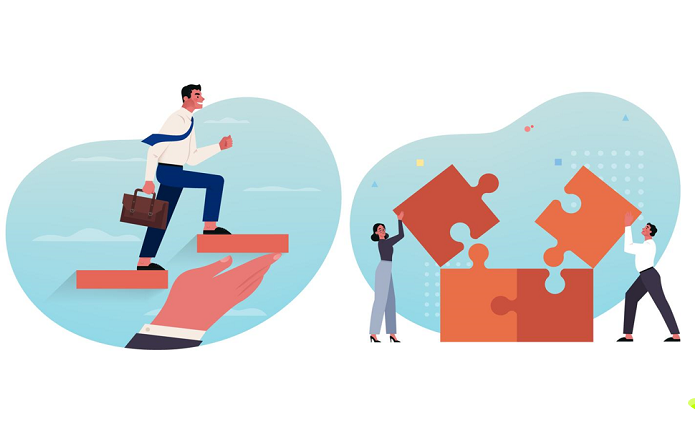
よくある失敗のケース
企業がよく陥るPDCAの失敗の事例で、よくあるケースは「目標を明確にせずとりあえず始めてしまう」ことです。
もちろん、直ぐに行動に起こすことは企業にとってとても大切な要素ですが、成果物やゴール感を可視化しづらくても、前提条件を作り他事例を参照しながら仮説を組み立てて、明確な“目標”を立てることが大切です。
仮説に基づいたゴール設計による具体的かつ詳細な計画(P)が、どういった実行(D)をすべきかを明確にしてくれます。
また、「やりっ放し(実行)になってしまい、サイクル(PDCA)の回転が止まってしまっている」という企業様も過去にみてきました。
多くの企業で“実行(D)“するまでは持っていけるのですが、担当者の交代や組織変更、事業方針の変化などにより、”実行“したままで数値やKPIを追いかけず放置されていることが多く見受けられます。
数字を直視するのは誰もが苦手で、場合によっては担当者の評価に繋がりかねないデリケートな部分ですが、組織全体で数字を”レビュー(評価/C)“して、具体的な”対策・改善(A)“を組み立てることが大切です。
加えて、一度きりのPDCAで終わらせず、連続して高速に進めれるようになると、より組織としてのバリューが上がります。競合他社が始めれてない未知な領域の事業であれば、ベンチマークする指標や数字もなく、仮説作りが難しいです。
ただ、そういった他社が踏み込めてない事業領域で、高速回転でPDCAを回せれると、他社に先んじて新しい事業領域でのポジションを固めることが出来ます。ただ単に、システムの導入やDXの活用というITの側面だけでなく、自社商品の展開や新規サービスの導入などにおいて、PDCAの徹底化と高速化は組織の総合力を高めてくれます。
PDCAを進める上で失敗しないためには?
ITやインターネットも“手段”であり、PDCAも業務改善など組織の課題の解決や目標に効果的に近づいていくために効果的な一つの“手段”であるともいえます。
こういった数多ある“手段”はコンサルタントやメディアでよく使われ、その言葉に振り回されたり、言葉遊びに終始してしまう危険性もはらんでいます。組織に所属する方々それぞれが、「なぜ」「どうして」「なんのために」「なにをいつまでにどうする」など、常に主体的に疑問を持ちながら、期限を設けてスピード感を持って進めていくことが肝要です。
地味で何回もプロセスを回し実行を繰り返しながら一歩ずつ前に進めていくイメージで、辛抱強さが必要になってきますが、皆さまの会社においても、PDCAで企業の継続的な成長を促しつつ、企業価値の向上に繋げていかれてみてはいかがでしょうか。
おわりに
nuloでは様々なビジネスの現場で色んな企業とお取引があり、ビジネスや組織の環境や課題に応じたご協力をさせていただいております。社内のDX化や自社のビジネス環境でのITや技術の取り込みなど課題や相談事がございましたら、是非、nulo株式会社にご一報ください。
【nulo お問い合わせフォーム】https://nulo.co.jp/ja/contact-us/